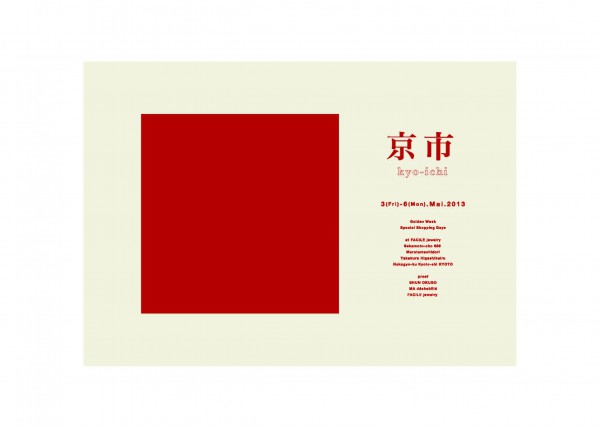先程MA DÉSHABILLÉの展示会に行ってきたので、忘れないうちにメモ。
先程MA DÉSHABILLÉの展示会に行ってきたので、忘れないうちにメモ。
展示会場に入るとデザイナーの明子さんは椅子に座っていて、こちらを見つめてcoucou~と笑顔で言った。
サンタマリア・ノヴェッラ(たぶん)の甘いけど凛々しい香り、シャンデリア、古い本、数年前のヴェネチアビエンナーレのアートの本(恐らく、アントワープの有名な美術商がキュレーションした展示会のカタログ)、机に置かれた美味しそうなキッシュ、フルーツ、ハンガーや壁に掛かったMAの部屋着の数々、MAを纏った美しいモデルの女性たち。ゆったりとした時間が流れる。
いつも明子さんに会うときも、明子さんの展示会に来るときも、安心する気持ちになるのはなぜだろうか。
以前、とある古い話を音楽家が書いた本で読んだことがある。
何年も昔、フランスに留学した日本の作曲科の学生がフランス人の先生に言われたこと
「君はソナタというものが何なのか分かるのかね?」日本人の青年は窮して答えることができなかった。
実はその答えとは、例えばパリの古いアパートの床の軋みだったり、ドアノブだったり、階段の手すりなんだと。
そのフランス人の先生が言いたかったのは、ソナタという形式というか、音楽のエスプリは、そういった些細な物の中だったり、何気ない人々の(生活の)中に宿るんだって言いたかったんだと思う。
無名の人達の歴史こそ、歴史の構築に捧げられる。
ソナタって何かというと、それってエスプリのこと、真のエスプリということだと思う。
MA DÉSHABILLÉの展示会や服のモード歴史のエスプリに満ちている。
表面をまねるだけのようなデザインではなく、服屋、もしくはメゾン、つまり、デザイナー、ポワレとかキャパンとかランヴァンとかマダムシャネルとか、彼らと、同じ連綿と続くモードの家族なんだと思う。
シルエットやディテールからその精神が立ち上ってくるように感じる。
例えば、現代のアジア人がストラヴィンスキーを世界中の誰よりも上手く演奏したり、
日本人が誰よりも情緒的にアントニオ・カルロス=ジョビンの曲やショパンの曲を弾くような、
もしくはアントニオ・カルロス=ジョビンが美しいショパンを弾くような、そのような感覚。
同じ音楽家の家族。同じモードのメゾンの家族。
何十年も前の生地を使って服を作ったり、古い服をリメイクして服をデザインする人達がいる。
もちろんそういうクリエーションも良いと思う。
また、並のデザイナーは過去のアーカイブから要素を取り出し、DJのようにそれらをリミックスして服を作る。
けれど、MA DÉSHABILLÉはそういう素材に依存しなくても、他の歴史の家族と同じようにモードを作ることが出来る。
過去のアーカイブを参考にしているとしても、デザインに不自然さが無い、嘘くささが無い、固さが無い。
私見だけど、日本人デザイナーの服は”固い”と感じることが多い。
MA DÉSHABILLÉの服自体が自然体で、あたりまえのようにモードの流れの中に佇む。これはすごいことだ。
例えば、僕の勝手な妄想だけど、ヨウジさんは川久保さんやイッセイさんよりも、この“血”が強いように思える。
明子さんも血が濃い。
現代的で、素晴らしい仕事をするデザイナーは日本にもたくさんいるけれど、
MA DÉSHABILLÉのような強いモードの家族の血をもったデザイナーを、僕は寡聞にしてほとんど知らない。
明子さんに会うといつもホッとするのは、モードの家に招いてもらっている気分になるからだと、書きながら考えた。
ちなみに、この部屋着に特化したコレクションは、タイで作られたヘンプや、オーガニックコットン、エジプト綿、オーガニックの染料、シルクetc、など、素材も優しく、かっこいいデザインの物ばかり。服の点数が以前よりも少なめだったのが、ちょっと残念だったけど、そんなことはどうでもよく感じてしまうほど良かった。
 『WHAT’S A FANTASISTA UTAMARO by QUOTATION』が先週発売されました。
『WHAT’S A FANTASISTA UTAMARO by QUOTATION』が先週発売されました。