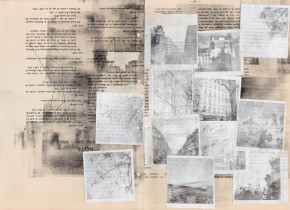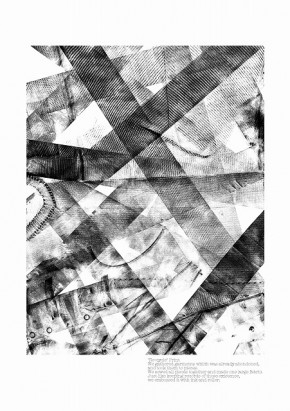2010年に結成されたデザインチーム「divka(ディウカ)」。2010年よりデザインチームとして設立され、ファッションを通して様々なプロジェクトを展開。実験的なプロジェクトの根底にあるのは、作品と出会った人々に時間や場所を越えてコミュニケートするという想い。
現在メンバーは2名で構成されており、田中崇順氏はセントラルセントマーティンズ美術大学出身。松本志行氏は文化ファッション大学院大学出身。
divkaはスペイン、バルセロナで開催される第4回Mango Fashion Awardsのファイナリストに選出。春に開催される最終審査に向け新作を製作中の2人に話を聞いた。
―デザインチームdivkaの設立経緯を教えてください
田中:松本とは以前勤めていたブランドで知り合いました。そこを退社してから、一緒に始めたプロジェクトがdivkaで、2010年のことです。始めたばかりの頃は資金的にも厳しくプロジェクトとして展開していました。その後、ブランドとして再スタートしたのは2011年の夏のことです。
―独立はずっと考えられていたのですか?
田中:学生の頃から漠然とですが考えていました。
松本:僕はこの人と一緒なら何か面白いことが出来るのかなと思いました。
―divkaの特徴とはどんなところにあるのでしょうか?
松本:divkaの特徴は、プリントと服のフォルムにあると思っています。どちらか一方に重きを置くというのではなくて、その相乗効果を目指しているということです。プリントもフォルムも、コレクションのテーマに基づいて行うリサーチや実験の過程から生まれるもので、コレクションごとに新しい事に挑戦しています。
―それは分業制でやられているのですか?
田中:2人しかいないので、2人で全部をやるのですが、基本的に僕はプリントと立体裁断を、松本はパターンを担当しています。フォルムのほとんどは、ボディーに布を当てて立体でつくっています。プリントもそうかもしれませんが、服の作り方、パターンには変わったものが多く、divkaの特徴が表れていると思います。
―田中さんはセントラルセントマーチンズを卒業していますが何を専攻されていたのでしょうか?
田中:ファッション科の中にはいくつかのコースがあるのですが、僕はファッションプリントというコースを専攻していました。ファッションプリントと言っても名ばかりのところもあって、自分の好きなことを自由に出来るのですが、服を作ることはもちろん、オリジナルのプリント製作も出来たのは、良い経験になったと思っています。在学中にはJohn GallianoやMiki Fukaiのアトリエで働かせてもらったこともありました。そこでも色々な経験をさせてもらいました。
―そもそもなぜセントマーチンズだったのですか?
田中:当時はMcQueenやChalayan、セントマーチンズ出身のデザイナーに憧れをもっていたんです。ファッションがやりたくてセントマーチンズには20歳の頃から通っていたんです。ファンデーションのクラスから通っていたのですが、先生からは「お前はファッションよりもアートをやった方が良いんじゃないか?」と言わたこともありました。
―先生は何を見てファッションよりアートに向いていると判断したのですか?
田中:自分でもはっきりとは分かりません。ただ、ファンデーションとは基礎クラスのことで、色々なことを学ぶところなのですが、ファッション的なアプローチよりもアート的なアプローチの方が得意に映ったのかもしれません。
今でもそうなのですが、コレクションを作る過程が変わっているんです。自分が何をやりたいのかを考え、コンセプトの核になるようなキーワードを挙げていく。それをいじくりまわしてどうにか表現の形まで持って行く。例えばプリントの柄の一つ一つにもキーワードがあるんです。
―一つ一つの柄にキーワードがあるのですか?
今回(12S/S)のコレクションでは、「Parallax」というテーマで物づくりの視線をずらしてみる、ということを考えていました。例えば、作業机には汚れが多く残っています。何かを描こうとしていた、そして服の形を決めようとしていた絵具や線がキャンバスからはみ出したりして出来たものです。逆から言うと、もし仮にキャンバスや紙がもう少し大きかったとしたら、それらは絵の一部分となるはずのものだったんですね。つまり、完成した絵を少しだけ違うものにする可能性を持っていたもので、そのあり得たかも知れない可能性を探ってみたい。明確な形をとる前の、あくまで潜在的な形というか・・・。そんなことを考えながら作ったのが今回のコレクションなんです。
―キーワードになるテーマはどこから出てくるのですか?
田中:リサーチしていく過程で決まっていきます。
―リサーチはどんなことをやられているのですか?
田中:図書館に行って本を広げてみたり、展覧会に行ってみたり。色々ですね。
―なぜリサーチをされるのですか?歴史を学ぶことが創造性に繋がるからですか?
田中:自分にとってリサーチはコレクションを始めるに当たってどうしても欠かせない作業なんです。リサーチといっても、ただ単に資料を集めることが目的なのではありません。リサーチブックを作っていく過程の中で、たとえば絵を描いてみたり、写真を撮ったりしながら、あれこれ試したり、考えてみたりすることが重要なんです。
これは最近思うことなのですが、僕個人の知識や経験にはどうしても限界があって、そこから発想されるものにもやはり限界がある。図書館で本をひろげることは、その限界をいささかなりとも超えることにつながるのではないか。リサーチが上手く行く、行かないにかかわらず、今はそんなことを考えています。
―divkaは海外の新進デザイナーを多数扱うオンラインショップNot Just a Labelでも扱われていますね。
松本:そうですね。海外で作品を発表するのは今の段階では難しいので、ネットを通して多くの方に観ていただく機会があるということはありがたいです。Not Just a Labelに載るようなって、早速連絡があったりと反響はあります。海外からの問い合わせが多いのですが、最近ではNYのショールームから連絡があり、今年の1月から契約しています。
―最初はプロジェクトとして始めたそうですがどんなことをやられていたのですか?
松本:初めは資金がなかったのでコレクションとして服を発表することが出来ませんでした。そこで、プロジェクトとして小物やTシャツを作りました。少しずつですが売れるようになって、ようやく一つのコレクションとして発表できるようになったのですが、2011A/Wまでは自分たちで縫製までやっていました。2012S/Sは量産も考えて、初めてのフルコレクションを発表することが出来たのですが、それまではほとんどが一点モノで、プリントもアトリエで染めていたりしていました。
Takayuki Tanaka at ITS#FIVE “the condition”
―田中さんはセントマーチンズ時代にITS#FIVEにも出展、ファイナリストとしてショーをされたそうですね。その時一緒に出展されていたのはMIKIO SAKABE, James Long, Heaven Tanuredja, Aitor Throupなどもう世界的に活躍している人が多いですね
田中:そうですね。一緒に出展していた方達が第一線で活躍しているというのは、凄く励みになっていると思います。
―ITSに出たことで何か変わったことはありますか?
田中:ITSを通じてお会いした方々から頂いた言葉が自分の糧になっています。その経験がなかったら、自分のクリエイションで勝負して行こうと決心できなかったかもしれません。
―ITSに出た時の作品はプリントが印象的でしたがセントマでもプリントを中心にやられていたのですか?
田中:当時から自分が目指していたのは、プリントとフォルムの相乗効果でした。プリントをただのサーフェイスデザインとは考えていなかったんですね。ドーリングやコラージュ、写真などを用いてコンセプトを様々な形で表現しようとしていたんです。同じようにフォルムにもこだわりをもっていました。ただボディの上でつくるだけではなく実験的な型出しをしていました。例えばハンガーに無造作にぶら下がっている作りかけのトワルを面白く思う。もちろんそれをそのままボディーに着せてもその面白みは再現できないのですが、何とか表現できないものかと色々な方法を繰り返す。それこそいい結果が出るまで何度も実験を繰り返しました。それ以外にも、普通ではあり得ないような裁断の仕方を無理やり試してみたりしていました。
―セントマーチンズの時から暗い色目の作品が多い気がします。
田中:特に暗い色が好きというわけでもないんですが。
松本:僕らがやっているプリントは確かに明るくハッピーなものではないかもしれないし、もしかしたら分かりやすいものでもないかもしれません。でもそこに面白さを感じるんです。
―Mango Fashion AwardsにはITS#NINEで日本人として初めてCollection of The Yearを受賞した西山たかし氏も出展します。まずそこがライバルになると思いますが
田中:そうですね。ただ結果がどうであれ自分たちのやりたい事をどこまで表現出来るかが大切だと思っています。
松本:まわりを意識せず自分たちのスタイルを貫きたいですね。